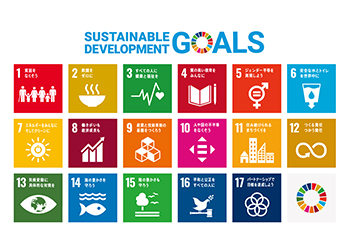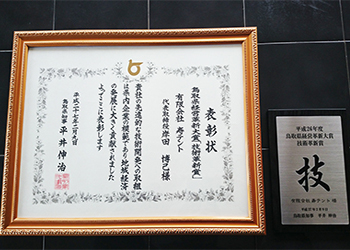湯梨浜町広報誌「広報ゆりはま 2009年9月号」より抜粋 / https://www.yurihama.jp/kouhou/21/21-9/
全国的な普及に「用具」も一役
専門委員会では「だれでも どこでも いつでも できるスポーツ」開発のためルールとともにグラウンド・ゴルフの用具の研究も行いました。
父親が経営する(有)寿テントに勤務していた岸田博己さん。知り合いだった朝井さんに依頼され、専門委員会に参加。グラウンド・ゴルフの用具開発を担当することになりました。
「『どこでもできる』という観点から、ゴルフのように地面に穴をあけるのではなく、ちょっと広い場所があればプレーできるように『ホールポスト』を作る必要がありました」。
ホールポストは金属製の1.5mほどの軽い用具で、持ち運びは簡単。上部には旗がついており、その下にある円形の枠にボールが静止すると「トマリ」となります。
「わたしは手先が器用で、ものを作ることが好きでした。いろいろなホールポストの形を試作しては、専門委員会で協議しました。ホールポストの下部の円形部分は、ガスボンベを型に丸くしました」と、岸田さんは試作の様子を語ってくださいました。
岸田さんは円形部分にボールが入りやすいよう、金属の骨組みをなるべく少なくするように工夫。さらに、円形部分中央の「ストッパー」と呼ばれる10cm弱の金属について、次のように説明してくださいました。
「ある日、当時一歳か二歳ぐらいだった長男が、『チーン』という鈴のような音をたてながら、テントの部品を持って遊んでいました」。岸田さんはこの様子にヒントを得て、テントの部品をそのままストッパーに使用。ストッパーにボールが当たることにより、円形部分をボールが通り抜けにくくなって、ホールインワンも出やすくなります。ボールが当たると、ストッパーが心地よい音をたてて、プレーヤーに「トマリ」を教えてくれます。
「父に『おまえは仕事もせずに、泊村に入り浸っている』とよく言われました。それくらい開発に夢中でした。
後年、仕事で北海道に出張した際、グラウンド・ゴルフをしている人を見て胸が熱くなったものです」と、岸田さんは目を細めました。